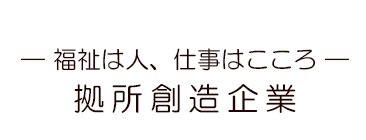�ꗗ�F
【福祉人の旅】2月末
今日で2月も終わりです。
2月は私にとって新しい道を大きく一歩踏み出そうとした月でした。
結果大きく一歩とはいかず、少しだけ前に進めたかな、という2月でした。
まさか後ずさりはしていないと思いたいのですが・・・
3月は2月の分も取り返し、大きく進めたら、と考えた月末でした。
【福祉人の旅】影響力
私たちが発する言葉は伝達力があります。
さらに責任ある人の言葉は影響力があります。
何気ない一言も影響力がある人の言葉だとどんどん影響を与えながら伝達していって
予期しない反応が起こることもあります。
責任ある立場の人は気を付けなければなりませんね。
【福祉人の旅】人間関係と価値観
人が2人以上集まるとそこには人間関係が成立し、必ず価値観の相違が出てきます。
人間関係の難しさは、この価値観の違いが最も厄介であることに象徴されるのではないでしょうか。
例えばどんなに仲良しでも、月日が経つにつれて価値観の相違が露呈してきます。
その価値観は、それぞれの人生経験や環境から作られており、なかなか一致することは難しいでしょう。
結局、良好な人間関係は、この価値観の違いをうまく乗り越えた場合に構築できるのではないかと考えます。
では、その価値観の違いを乗り越えるために必要なことは何でしょう。
それは、人は結局一人では生きていけないということに気づけるかどうか、ではないでしょうか。
人は誰かと関わりを持たないと生きていけないのだから、価値観の違いを理由に争うことは意味がありません。
良好な人間関係のためには、お互いの価値観を認めること。
それが出来れば価値観の違いは乗り越えられると私は考えます。
【福祉人の旅】新しいこと
最近は新しいことについて考える機会がとても多くなっています。
例えば新規事業であったり、新しいルールであったり・・・
新しいことを考えるときはワクワクする反面、プレッシャーにつぶされそうにもなります。
見込が間違っていたら、とか、受け入れて頂けなかったら、などなど。
たらればを考えればきりがありませんが、少しでもリスクを減らしたり、可能性を広げるためには
想像を膨らませなければなりません。
そのためにはいろんな情報を入手し、思い込みを極力排除しながら考え続けるしかありません。
【福祉人の旅】リンゲルマン効果
リンゲルマン効果というものがあります。
人間とは集団の中に紛れると一人の時と比べてパフォーマンスが低下してしまうという心理効果です。
実験では、一人で綱引きをしたときに発揮した力を100とした場合、
二人ですると93%、三人ですると85%、8人でした時にはなんと49%まで低下したそうです。
これは人間が集団の中で作業すると無意識に手抜きをしてしまうことから「社会的手抜き」とも呼ばれます。
無意識ですからなかなか対策も難しいのですが、モチベーションが関係しているともいわれます。
綱引きのプロの方たちで同じ実験をしたところ、ほとんど力の低下は現れなかったそうで、
モチベーションが高い集団ではリンゲルマン効果が表れにくいそうです。
モチベーションを上げるには報酬であったり、適正な評価であったりいろいろですが、
まずは集団全体だけでなく、個々をしっかりと評価してモチベーションを上げることが大切なようです。
【福祉人の旅】管理職の仕事
スタッフから管理職になると、仕事の内容が変わるのは当然として、心構えも変えなくてはなりません。
たとえば、部署で行うべき大事な仕事が入り、期限までに失敗せずやり遂げなくてはならないという場合、
多くの方が考えるのは、まず「自分でやろう」ではないでしょうか。
確かに、経験の深い自分が行ったほうが、仕事が早く正確で、クオリティが高いことは多いでしょう。
気持ちしては理解できますが、この考え方が正しいとはいえません。
与えられた仕事を自分で処理する能力は、スタッフとしての能力であり、管理職としての能力ではないのです。
管理職は自分の時間、プラス、スタッフがもつ時間も考慮し、全体のパフォーマンスを考えるべき立場です。
自分は、スタッフより付加価値の高い仕事を行い、そのほかの仕事は、極力人に任せていく方法を考えなくてはなりません。
常に、個々のタスクの「費用対効果」を考え、まず部下に振ることを検討し、能力が及ばない場合に、
自分が乗り出していくという形にすべきでしょう。
あらゆる仕事を自分で処理して、組織が回っている場合、あたかも「自分は仕事ができる」と勘違いしてしまいがちになります。
しかし、それは、自己満足に過ぎません。
管理職の仕事とは、組織全体を自分と考え、誰がどの仕事を担当することが組織全体として、効果的に業務が進むか、
時間を効率的に使うことになるか、を考えることが大切なのだと思います。
管理職になった人は、ぜひ、「自分でやりたい病」を治療するように気をつけましょう。
【福祉人の旅】面接
今日は私たちの施設でお仕事をして下さる方とお話しさせて頂きました。
お仕事に対するお考えやご希望をお聞きし、ぜひ仲間になって頂きたいとお話ししたところ、
快くお受けしてくださいました。
また心強い仲間が増えることになり頼もしい限りです。
【福祉人の旅】お願い
コロナウイルスの感染者の増加や花粉の飛散の開始などのニュースが報道されています。
どちらも必須のアイテムとしてマスクが考えられますが、感染症の予防にマスクはあまり効果的ではありません。
予防のためにマスクを大量に購入されている方が急に増え、日用品店では品切れが続いているようです。
結果マスクが品薄になり本当に必要な花粉症に苦しむ方や、咳やくしゃみの症状のある方にマスクが行き届かないそうです。
また、マスクの大量発注や大量出荷に追われる日用品販売店や通販サイトは大変な状況で、
マスク以外の製品の出荷も滞りがちとのことです。
事実私たちの施設もご利用者様の紙パンツなどの必要なものがなかなか届かず、在庫が少なくなり心配な状況です。
どうかマスクの買い占めや大量購入をお控えいただきます様、何卒よろしくお願い致します。
【福祉人の旅】ツァイガルニック効果
心理学用語に「ツァイガルニック効果」というものがあります。
人は、完成した課題よりも未完成の課題の方をよく憶えている傾向がある、という法則です。
テレビでコマーシャルになる前に、「この後、大変なことが!」などというテロップが流れると、
気になってチャンネルを変えられなくなるのは、このツァイガルニック効果が働くためだそうです。
例えば膨大な量の仕事をこなそうとしたときに、キリのいいところまでやってあとは明日にしようとするより、
キリのいい少し手前でやめ、翌日続きをするようにするとすぐに取り掛かれるそうです。
何日も継続する仕事の時には効果的かもしれません。
【福祉人の旅】セミナーに参加して
昨日、あるセミナーに参加させて頂きました。
医療・介護報酬改定の内容から今後の医療福祉の方向性を考える内容で、大変勉強になりました。
そこで、なるほど!と思った内容を一つ。
最近よく聞かれるキーワードで、「人生100年時代」「働き方改革」というものがあります。
それぞれ別々に内容を考えると、
「人生100年時代」は、平均寿命が延び、それにより医療介護費用が上昇していく、そのなかでどのようにして
安心安全な社会を構築するか・・・という感じでしょうか。
「働き方改革」は、AIやロボットの進化のなかで人間ができることに注力し、更には多種多様な働き方を創出し、
全ての人が働ける環境を・・・・といったところでしょうか。
ところが、この二つのキーワードを一緒に考えると少しニュアンスが変わってきます。
寿命が延び人生100年となると、今まで働き手と考えられていた20~60歳という年齢構成が、20~80歳と変わっていきます。
すると80歳まで正社員として働く人が増えるでしょう。ですが、やはり80歳の方に20歳と同じ働き方を求めるのは現実的に厳しく、
夜勤や長時間労働は難しくなります。ですが、若手の人口の減少により高年齢の方を活用していかなければ事業が
成り立たなくなります。そのためには、例えば正社員の勤務内容を年齢別に多様化させ、労働力を確保する必要があります。
今は医療福祉の現場では2交替や3交替が主流ですが、高齢の方にお願いするなら4交替、5交替であったり、
週休3日、4日といった改革をしていく必要がある・・・という内容が見えてきます。
もっと我々企業側がもっと積極的に考えていかなければならなくなりそうです。